
|
6-2 中学校
6−2−1「心を育む環境教育」への取り組み(環境学習推進拠点校として)
高城英子(松戸市立小金南中学校)
広範囲にわたる環境教育ですが、本校では「生徒自身が環境や環境問題に関心を持ち、科学的な認識にたち、よりよい環境づくりに主体的に取り組んでいける心豊かな生徒の育成」に向けた「心を育む環境教育」と位置付け取り組んできました。
まず私たちは、環境教育で大切なことは、ただ自然を学んだり、自然破壊や公害問題を学んだりするだけでなく、何を改善し、利害や立場の違った者同士がいかに手を結びあい、新しい方向性を見いだすのかという前向きな考え方で取り組むことであると考え、このような考え方を身に着けるには、受け身の学習ではなく、学習者が実際に体験し、その中で自ら感じ、気づいていく「参加体験型」の学習が適していると考えました。参加体験の中で感じたことをそのままにせず、更に話し合い活動などを取り入れ、学習者同士がお互いに関わり合いながら学習を組み立てていく授業を取り入れていくことにより、確かな気づきがあり、内発的な行動へと結び付いていくものと考えたのです。
さて、具体的にはどのような場面で環境教育を実践していくのか。私たちは次の4つを基本方針として進めてきました。
・ 中学生は感受性の強い年頃なので、まず、学校行事などを活用した体験学習を通して様々な美しさにふれさせ自然の美しさを知り、より美しいものを求める豊かな心を育てる。
・ 特別の教科で「環境」について扱うのではなく、全ての教科において環境や環境問題に対する科学的認識を深めさせ、身近な環境や生活に目を向けさせる。
・ 参加体験型の授業を道徳や学級活動の中でも積極的に取り入れるなど、学習指導法を工夫し自ら「気づき」、意欲的に学ぶ生徒を育てる。
・ 生徒会活動や行事などを利用し、実践活動にも目を向けさせ、環境に対する責任ある行動を体験的に身に着けさせる。
実際にはどのように進めたのか、実践の中から見てみますと…
1 教科の中で
A 年間学習計画の中での位置付け
環境教育という視点から各教科・領域の見直し、4月当初の年間学習計画立案の際に各学年ごとに抜き出してみました。道徳・特活領域では研究も不充分でしたので、仮の案とし、実践の中で検討していくことにしました。
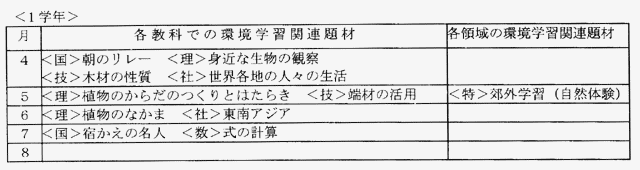
前ページ 目次へ 次ページ
|

|